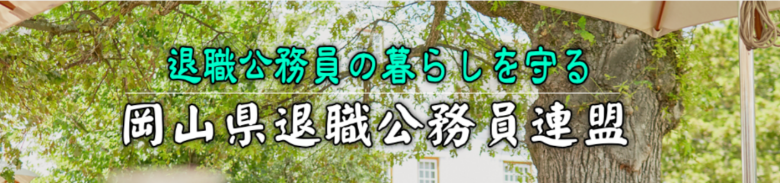岡山県退職公務員連盟
過去の学校だより
 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度
令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度
令和7年度
(登下校ボランティア) ◆友人からのメール。「今年から子どもたちへの登下校ボランティアに参加して、子どもたちの 元気な声から私の方が元気をもらっています。でも、子どもたちの中には、声をかけても見向き もしないで通り過ぎる子がいます。そんなときは朝からストレスがたまります」と。 実際、声をかけても無視をするように通り過ぎていく子どもを見ると、そばに行って声を荒げた くなることは自分の体験からも実感するところ。 ◆20年ほど前、機会があってノートルダム清心学園理事長(当時)の渡辺和子さんに、そのよ うなときカーッとなる自分を打ち明けた。 「そうですか。あなたは声をかけたのに、子どもは返事をしてくれなかった。それであなたは 一つ損をしましたね。ならば、もう一つ、返事をしてくれなかったその子を許すという二つ目の 損もしてあげてください」と。 さらに「返事をしなかったその子、実は心の中では、あなたからの一声をほかのどの子よりも 必要としているのかもしれませんよ」と。 ◆こちらから声をかけても無視される損、それをまた許す損。二つの損を微笑んで受け止める ことは決して易しいことではない。 朝夕の厳しい暑さ、寒さの中を笑顔で子どもたちを迎えておられる地域ボランティアの方の姿 から、何かしら目に見えないあったかいものが伝わってくるのである。 (2025.8.28岡山東支部松浦) (老後!何色?) ◆雨の時季になると思い浮かぶ「城ヶ島の雨」(北原白秋)の歌に、「利休鼠の雨が降る」とい う一説がある。「利休鼠」とは緑がかった灰色のことで、抹茶の緑色を想起させる色合いから 利休の名を借りてそう呼んだらしい。 ◆今話題のファジアーノのチームカラーは赤系の臙脂色であるが、同じ赤系にも今様色、柿 色、唐紅、鴇色とデリケートな色の違いで表現がいろいろと変わるようだ。このように色に対し て極めて多彩で、繊細な日本人の感性は世界に類を見ないという。 ◆さて、日本人は昔から四季折々の自然の変化から季節を感じ取り、人生を四季と色に関連 づけてきたのはさすがである。 10代から20代は 青色で 青春 30代から40代は 赤色で 朱夏 50代から60代は 白色で 白秋 70代以降は 黒(紫)色で 玄冬 ◆この考え方は中国古代の五行説が由来とされている。しかし、この時代には現代のような 人生100年を想定してなかったからであろうか、70代以降で終わってしまっている。 ならば、今に生きる80代・90代の老後の人生は何色であろうか。黄色(健康)、銀色(知的)、 緑色(安全)・・・・などいろいろ出てきそう。 しかし、「わが老後は薔薇色!」はないよなあ。これは失礼しました。 どうやら、自分の老後の色は自分に合った無理のない色で塗っていくことになるのかなあ。 (2025.7.10岡山東支部事務局子) *2025年度から日公連の「退職公務員新聞」の発行が偶数月になったことに伴い、「帯封コラ ム」も偶数月に発行します。 (県退公連総務部) (ある朝、突然に) ◆「ある朝、目をさますと自分がベッドの中で大きな毒虫に変わっているのに気がついた」。こ の唐突な書き出しで始まる小説は、カフカ(チェコ)の有名な「変身」である。 学生時代、この冒頭の「ある朝〜」の部分がひどく気に入って、「〜」の部分を勝手に言い換 えては一人密かに、心躍らせていたことを思い出す。 「ある朝、目を覚ますと宝くじで100万円当たっていた」 「ある朝、目を覚ますと英語がペラペラになっていた」などど。 ◆しかし、あれから60年後の今はとてもそんな悠長なことを言っては折れなくなってきた。 ある日 ・車の運転席から手を伸ばして、後ろの座席にものを置こうとして腰が〜。 ・座敷の電気コードにつまずいて、コロリと転んで脚が〜。 ・喉の麻痺で、声が〜。 などなど。 これらは、すべて「突然」に、「前触れもなく」「不意」に変身を余儀なくされる。 「オール ザ サットン」(“All the sudden”) ◆われわれは、まさに「突然」何がやって来てもおかしくないと言える世代である。 さあ、どうする。 日頃の健康への心配りとともに、一方では避けられない「突然の変身」のことを考えると、 「明日」ではなく「今日」という日を、いや「今」を大切にということかなあ。 (2025.4.30岡山東支部事務局子) |